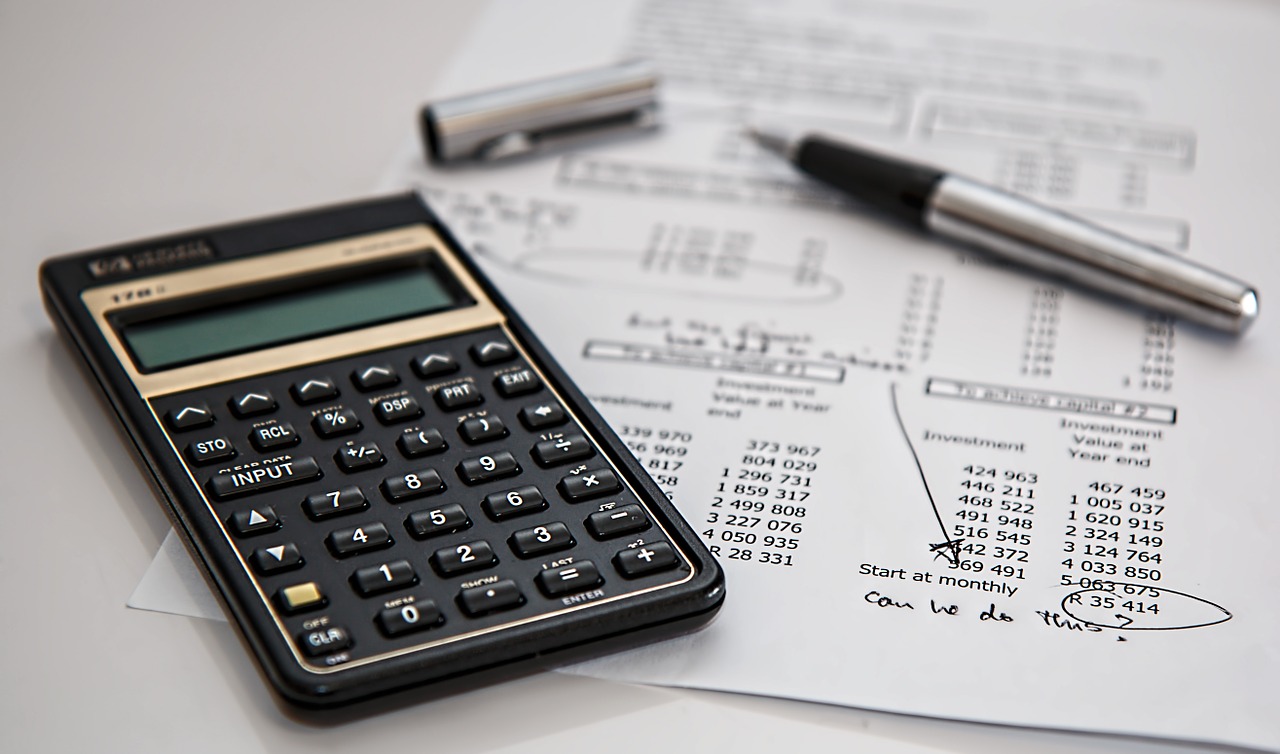気づけば・・・
サラリーマンに戻っていた
サラリーマンは安定はしているが、税金があまりにも高すぎる
今回は自営の頃に利用していた「小規模企業共済制度」について書いていきたい
小規模企業共済制度とは?
加入することにより、経営者や役員の所得税が減ります。
そして、掛け金はソコソコの利子がついて、廃業時や退職時に返ってきました。
小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」。 掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
中小企業退職金共済制度(中退共)との違いは?
「小規模企業共済制度」と「中小企業退職金共済制度(中退共)」の違いは?
対象が経営者か従業員かという事です。
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主、共同経営者、会社等の役員を対象とした経営者の退職金共済制度みたいなものです。
一方、中小企業退職金共済制度は、中小企業の従業員を対象とした退職金共済制度です。

PublicDomainPictures / Pixabay
小規模企業共済のメリット
税法上のメリット 個人の所得控除の対象
個人事業主・会社役員が加入する小規模企業共済は、あくまでも経営者個人が加入するものですので、事業上の経費にはなりません。
経営者個人の所得控除の対象です。
最大120%相当額が戻ってくる
将来共済金が戻ってくるときは、掛金納付期間に応じ最大120%相当額が戻ってくるのが2番目の魅力です。
※納付期間が20年以下だと、元本割れします(任意解約の場合)
退職金とみなされるので、節税になる
小規模企業共済は、積立時は節税になるが、解約時には税金を払わなればならない。
しかし、受け取る共済金(解約手当金)は、個人事業主であれば「退職所得」になるので、「事業所得」などに比べて税負担が大幅に軽くなる。
退職所得が事業所得よりも税負担が軽くなる理由 「事業所得」の場合:収益-費用=所得 「退職所得」の場合:(退職金-控除額)×1/2=所得 計算式は上記のとおりです。 退職所得の場合、「控除額」や「×1/2」があるため、課税対象となる所得が大幅に小さくなり、 税負担が軽くなります。
つまり、小規模企業共済の共済金は退職所得になるため、事業所得の一部を掛金で積立てて共済金を退職所得として受け取る手法が節税対策でよく使われています。
無理のない額を積立できる
掛け金を月1,000円~70,000円の間で自由に設定することが可能です。
貯金の習慣のない個人事業主には、ピッタリの制度です。
貯金は難しいが、銀行引き落としなら・・・
資金繰りに困ったときの資金調達の手段になる
資金が一時的にショートするというのは、よくある話です。
解約しなくても、積み立てた金額の範囲であれば、いつでも借り入れが可能です。
小規模企業共済のデメリット
元本割れのリスク 20年未満かつ任意解約の場合
20年未満で解約すれば、元本を下回ります。
しかし、2015/08に法律が改正されました。
理由を問わず「退職した事実」がある場合には、払い込んだ金額以上を共済金として受け取ることができます。
ex.掛金月額1万円で、平成16年4月以降に加入
| 掛金
納付年数 |
掛金累計
(円) |
共済金A
(円) |
共済金B
(円) |
準共済金
(円) |
| 5年 | 600,000 | 621,400 | 614,600 | 600,000 |
| 10年 | 1,200,000 | 1,290,600 | 1,260,800 | 1,200,000 |
| 15年 | 1,800,000 | 2,011,000 | 1,940,400 | 1,800,000 |
| 20年 | 2,400,000 | 2,786,400 | 2,658,800 | 2,419,500 |
| 30年 | 3,600,000 | 4,348,000 | 4,211,800 | 3,832,740 |
共済金受け取り時に課税される
将来、共済金(解約手当金)を受け取った際には、受け取った年に課税されるので注意が必要です。
つまり、受け取った年に一気に税負担が増すのがデメリットです。
ただし、トータルで払う税金は少なくてすみます。

jill111 / Pixabay
小規模企業共済制度への加入は早めに・・・
業種によって違いはありますが、従業員5名~20名ぐらいが「小規模企業」とみなされ、加入可能です。
そして、一度加入してしまえば、事業拡大の後に続けることは可能です。
業種にもよりますが、従業員数が一定数以上を超えると「小規模企業」ではないと見なされ、 加入できなくなります。 そして、要件を満たしている時に一度加入しておけば、事業拡大後も続けることは可能です。 このような理由から、小規模企業共済制度に興味がある方は、起業したら早めに( 会社が大きくなる前)に加入を検討しておくことをお勧めします。
小規模企業共済制度の加入方法は?
というわけで(?)気になる「小規模企業共済制度」に加入するためには・・・
以下に貼り付けた「中小機構」公式HPで確認してください
という事で、今回は自営を始める前に知っておいたほうがいい「中小企業共済制度」の概略でした。
税金の計算等に慣れていない人には、「税理士」または「公認会計士」に相談する事をお勧めします。
税金のプロが近親者にいる管理人1も、自営していた頃にはお金を払って「税理士事務所」にお世話になっていました。
責任逃れができるので、安心して本業に打ち込めます。
読了、ありがとうございました
また、どこかで・・・